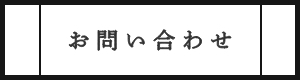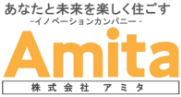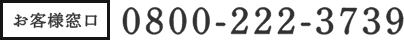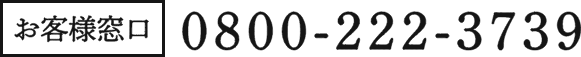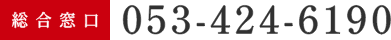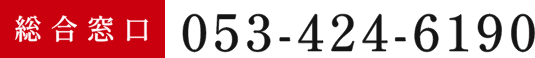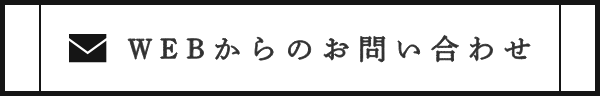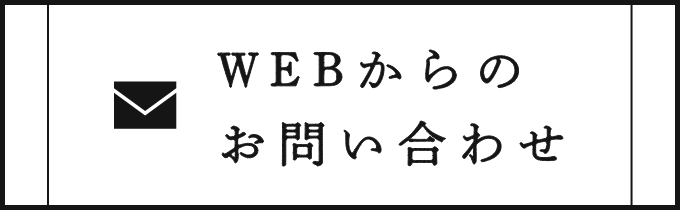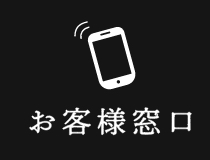「就活のスタートはいつから?27卒新卒生向けガイド」
目次
1. はじめに:就活スケジュールはなぜ気になる?
2. 就活スケジュールの全体像
3. 27卒における主な就活期間の流れ
4. 本格的なスタート前にやっておきたい準備
5. インターンシップの重要性と参加のタイミング
6. 自己分析・業界研究・企業研究の進め方
7. エントリーシート(ES)・履歴書の作成ポイント
8. 選考対策:筆記試験・面接・グループディスカッション
9. オンライン選考が増えるなかでの対策
10. 27卒ならではの最新動向:コロナ禍後の就活と企業側の変化
11. OB・OG訪問・キャリアセンター活用のコツ
12. 内定獲得から入社までにやるべきこと
13. まとめ:自分らしい就活をスタートさせよう
1. はじめに:就活スケジュールはなぜ気になる?
近年、日本の新卒採用は「採用広報開始時期」や「選考解禁時期」がしばしば見直され、就職活動のスケジュールは毎年変化しているといえます。特に、大学3年生の秋から冬にかけては、インターンシップの参加や本格的な就活準備のスタートが一般的となりました。その一方で「早期選考」を行う企業が増えていることや、IT企業・外資系企業などが独自の早期スケジュールを設定しているケースも多く見られます。
27卒(2027年3月に大学を卒業予定)の学生にとっては、具体的に「いつから動き始めればいいのか」「どのタイミングで何をしておけばいいのか」という疑問が生まれることでしょう。本コラムでは、27卒向けに標準的な就活の流れを踏まえつつ、最新の動向や注意点を織り交ぜながら、就活の始動時期と準備のポイントを解説していきます。

2. 就活スケジュールの全体像
一般的には、大学3年生の夏から秋頃にインターンシップが活発化し、3年生の3月(つまり卒業の前年の3月)に企業の採用広報が解禁され、その後6月から本格的に選考が始まる、という流れがここ数年の「建前」として存在してきました。経団連(日本経済団体連合会)が示す「採用選考に関する指針」は年ごとに細かくアップデートされるものの、ここ数年のトレンドはほぼこの枠に沿っています。
しかし実際には、経団連に加盟していない企業(スタートアップや外資系など)では、もっと早い段階でインターンシップを開催し、優秀な学生に内々定レベルのオファーを出すことも増えてきています。またコロナ禍以降、オンラインでの説明会や選考を積極的に取り入れる企業が急増し、スケジュールの型がさらに崩れ始めています。こうした状況を踏まえると、学生側が「いつから動けば間に合うのか」を判断するのは難しくなってきています。

経団連のスケジュールと「実態」のギャップ
-
経団連加盟企業の大まかなスケジュール(従来)
-
3月:採用広報(説明会)開始
-
6月:選考解禁(面接開始)
-
10月:内定式
-
-
実態
-
インターンシップは大学2~3年生の夏から秋にかけて募集・実施
-
早期選考や通年採用を行う企業が増加
-
外資系やIT大手では3年生の春頃から選考が始まるケースも
-
このギャップを認識し、早めに動き出すことが就活における大きなアドバンテージになります。

3. 27卒における主な就活期間の流れ
3年生(2025年4月~2026年3月)
-
春(3年生の4~6月頃)
-
大学の授業が始まって間もない時期ですが、ここから就活に対する意識づけを始めるとよいでしょう。自己分析や業界研究を少しずつ進めるほか、興味のある業種・企業があればインターンシップ情報の収集をしておくのがおすすめです。
-
外資系企業や一部のIT企業では、3年生春の段階からインターンの選考が始まることもあるため、特に志望度が高い場合は情報収集を怠らないようにしましょう。
-
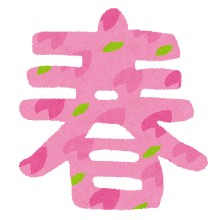
-
夏(3年生の7~9月頃)
-
本格的なインターンシップシーズン。1~2週間程度の短期インターンから、1~2ヶ月ほどの長期インターンまで、企業によって多種多様です。もし就活を早めにスタートさせたいのであれば、このタイミングで少なくとも1社はインターンに参加してみるのが望ましいです。
-
インターンを通じて業界や企業の理解を深めるだけでなく、実際の仕事を体験することで自分に合う・合わないを判断できるメリットがあります。
-

-
秋~冬(3年生の10~12月頃)
-
夏のインターンを通じて自己分析や企業研究がある程度進んだはずです。興味のある業界や企業をさらに絞り込んだり、追加でインターンや会社説明会(早期開催分)に参加することで理解を深めましょう。
-
この頃から一部企業では早期選考を進めている可能性があります。「ベンチャー企業」「外資系企業」を目指している場合は特に注意が必要です。また、エントリーシートの書き方や面接対策も少しずつ始めておくと余裕が生まれます。
-

-
年明け~3月(3年生の1~3月頃)
-
経団連加盟企業の「採用広報解禁」が3月から始まるため、企業説明会や合同企業説明会が本格化します。就活サイトに登録し、エントリーを始め、説明会に参加する学生も一気に増えていくでしょう。
-
ここまでに自己分析、業界・企業研究、エントリーシートのひな形作りはある程度完了させておくとベストです。また、3月の解禁後は説明会の予約が殺到しやすいので、こまめに就活サイトをチェックしておきましょう。
-

4年生(2026年4月~2027年3月)
-
春~初夏(4年生の4~6月頃)
-
経団連スケジュールに則った企業の選考が本格化する時期です。面接、グループディスカッション、筆記試験などが集中し、就活生にとってはかなり忙しくなる季節といえます。
-
自己分析や企業研究はもちろん、面接対策やグループディスカッションの練習が重要になります。大学のキャリアセンターやOB・OG訪問を活用して、具体的なアドバイスをもらいましょう。
-


-
夏~秋(4年生の7~10月頃)
-
多くの企業がこの頃までに採用選考を終了し、内定出しを行います。6月~7月に面接を終えた学生から内定を受諾し、10月の内定式を迎えるという流れが一般的です。
-
ただし、ここからの時期でも選考を続ける企業は一定数ありますし、追加募集や通年採用を行う企業もあります。もし春先の選考でうまく結果が出なかったとしても、諦めずに情報収集を続けることが大切です。
-

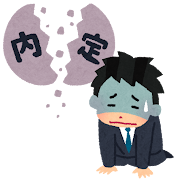
-
卒業間近(4年生の11月~卒業直前)
-
内定承諾後は、卒業研究・論文など学業との両立を図りながら、入社準備や卒業旅行などのイベントを計画する時期になります。企業によっては内定者向けの研修や懇親会が行われることもありますので、積極的に参加して同期との人脈を築くと良いでしょう。
-

4. 本格的なスタート前にやっておきたい準備
就活が本格化する前に、以下のような準備を進めておくことで、混乱や焦りを最小限に抑えることができます。
1. 自己分析
-
自分の強み・弱み、価値観、興味関心などを明確化する。これによって業界研究や企業研究の方向性が定まり、エントリーシートや面接で一貫した自己PRができるようになる。
2. キャリアビジョンの仮設定
-
「将来どんな社会人になりたいか」「どんな仕事を通じて社会に貢献したいか」を考え、そこから逆算して業界・企業を絞り込む手がかりにする。
3. 就活サービスの登録・情報収集
-
大手就活サイト(リクナビ、マイナビなど)だけでなく、ベンチャー企業に特化したサイトや外資系企業に特化したサイトなど、自分の興味や強みと合致するプラットフォームにも登録しておく。
-
SNS(特にTwitterやLinkedInなど)も企業情報や就活テクニックが集まりやすいので活用を検討する。
4. 面接対策・コミュニケーション能力の強化
-
友人同士やゼミ、サークルなどで模擬面接やグループディスカッションを体験しておく。大学のキャリアセンターで模擬面接の機会を設けているところも多いので、積極的に利用してみる。
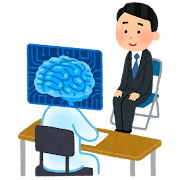
5. インターンシップの重要性と参加のタイミング
就活の早期化が進む中、インターンシップは単なる「職業体験」の域を超えて、企業との接点を早期に作り、選考で有利になるための重要な機会となりました。特に早期選考を実施する企業では、インターン参加者の中から選考に進む学生を優先的に選ぶケースが多いため、「インターン参加=選考ルートの一部」と考えている企業も存在します。
インターンシップのメリット
1. 企業理解が深まる
-
具体的な業務を経験することで、その企業の社風や働き方、社員の雰囲気を肌で感じられる。短期インターンであっても、説明会だけでは得られないリアルな情報が得られる。
2. 自己アピールのチャンス
-
インターン中の行動や成果が選考に影響する場合もある。チームワークや自主性をアピールできれば、後の面接やエントリーシートでのエピソードとしても活用できる。
3. 志望動機を具体的にできる
-
「なぜこの企業なのか」を答える際に、インターンで得た具体的なエピソードを盛り込むことで説得力が増す。


参加のタイミング
-
短期インターンシップ(1日〜1週間程度)
-
大学3年生の夏休みや冬休みを中心に募集されるケースが多い。企業によっては1~2dayのプログラムもあり、複数の業界や企業を見比べる良い機会となる。
-
-
長期インターンシップ(1〜3ヶ月以上)
-
スタートアップやIT企業で盛ん。学業と並行して平日数日働くケースも増えている。業務を深く体験し、プロジェクトに主体的に関われるため、成長機会が大きい反面、時間的負担は大きくなる。
-
就活を有利に進めるためにも、3年生の夏頃から複数の企業のインターンに挑戦してみるのがおすすめです。

6. 自己分析・業界研究・企業研究の進め方
自己分析
1. これまでの経験棚卸し
-
中学・高校・大学での部活やサークル、アルバイト、ボランティアなど、人生の節目において何を学び、どんな行動をし、どんな結果を得たかを振り返る。
-
ポイントは「なぜその行動を取ったのか」「どう感じたのか」を言語化すること。
2. 他者からのフィードバック
-
友人や家族、ゼミの先生、アルバイト先の上司など、身近な人に「自分の強み・弱み」や「どういうところに魅力を感じるか」を尋ねてみる。意外な気づきが得られることも多い。
3. 価値観の確立
-
「何にやりがいを感じるか」「どんな社会人として生きたいか」を言語化する。就活中に迷ったときの軸を明確にしておくことで、企業選びに一貫性が生まれる。
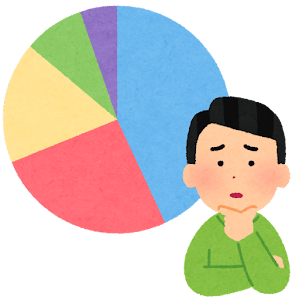
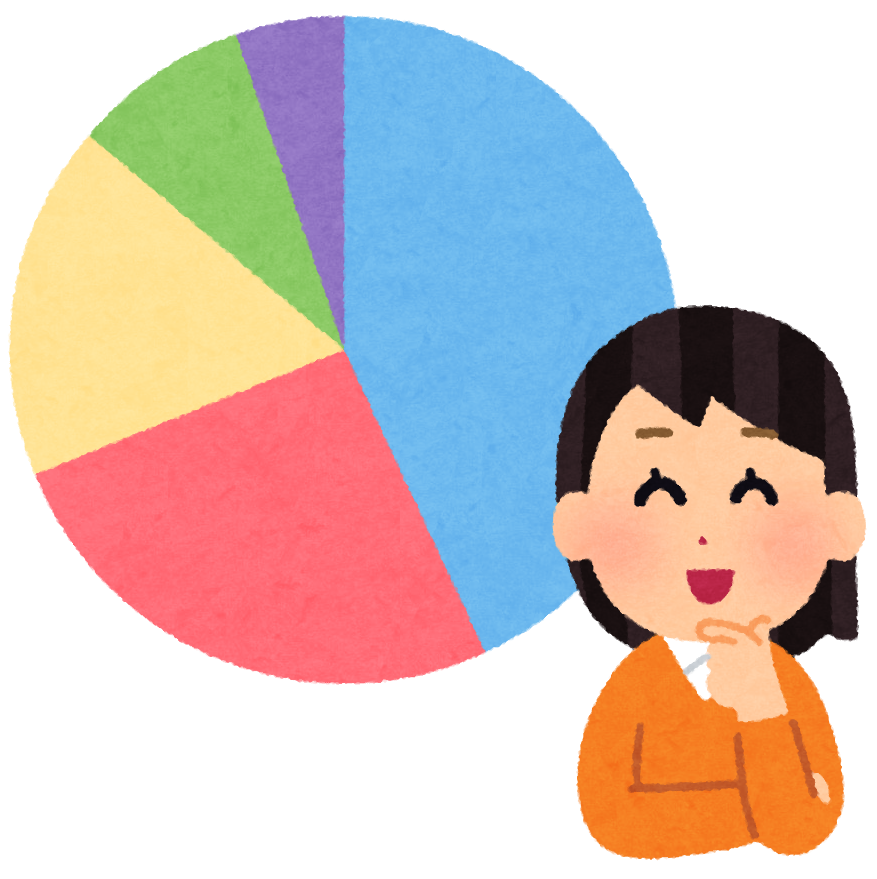
業界研究
1. 業界の全体像を把握する
-
金融業界、メーカー、IT業界、マスコミ、商社など、主要な業界ごとの特徴やビジネスモデルをざっくり理解する。
-
業界マップや経済誌の特集などを活用すると効率的。
2. 動向・課題の把握
-
「コロナ禍後でどう変化したか」「IT化やDXがどのように進んでいるか」など、業界全体の課題を知ることで、面接やエントリーシートに深みを与えられる。
3. 競合企業の比較
-
業界大手と中堅企業、スタートアップの違い、業務内容や強みの違いを比較することで、自分に合った企業規模やビジネスモデルを絞り込みやすくなる。

企業研究
1. IR情報・採用ページの熟読
-
上場企業であればIR資料(決算短信や有価証券報告書)を読み、業績や経営戦略を確認する。非上場企業でも採用ページやプレスリリース、ニュース記事などから情報を収集する。
2. 社長・経営陣のメッセージを読む
-
企業のビジョンや価値観、社風は経営陣の考え方に影響されることが多い。自分の価値観との相性を確認するためにも、トップメッセージはしっかり読む。
3. 口コミサイトやSNSでの評判も参考に
-
実際に働く社員の口コミサイト(OpenWorkなど)や、SNS上での評判も参考材料にするとよい。ただし、情報の真偽や一方的な意見である可能性があるため、あくまで「参考」として鵜呑みにしないことが重要。


7. エントリーシート(ES)・履歴書の作成ポイント
エントリーシートと履歴書の違い
-
エントリーシート(ES)
-
企業ごとに設問やフォーマットが異なる。自己PR、志望動機、学生時代に力を入れたことなどが問われる。文字数制限も多様。
-
-
履歴書
-
学校指定のものや市販のフォーマットを使うケースが多い。基本情報(学歴・職歴・資格など)を正確に記入し、誤字脱字や記入ミスに注意。
-

作成のコツ
1. 設問の意図を読み取る
-
「学生時代に力を入れたこと」といっても、企業が本当に知りたいのは「その行動の背景や学び、成長をどのように捉えているか」。行動の結果だけでなく、過程や思考プロセスを具体的に書く。
2. 結論ファースト・具体例重視
-
ダラダラと背景を書くのではなく、まず結論を書き、その後具体的なエピソードを交えて補足するスタイルが読み手にとってわかりやすい。
3. 企業との接点を示す
-
志望動機や自己PRなどでは、企業の理念や事業内容と自分の価値観がどのように合致しているかを明確に示す。単なる「憧れ」や「有名だから」は避け、具体的な理由を言語化する。
4. 誤字脱字・フォーマット崩れに注意
-
どんなに内容が優れていても、基本的なミスがあると印象が悪くなる。提出前に必ず複数回チェックする。

8. 選考対策:筆記試験・面接・グループディスカッション
筆記試験
-
WEBテスト(SPIなど)
-
言語・非言語・性格検査が中心。問題の形式に慣れておくためにも、市販の問題集やアプリを使って練習しておくと良い。
-
性格検査は嘘をつくと矛盾が生じやすいため、自分の考えを素直に答えるのが基本。
-
-
一般常識・時事問題
-
新聞やニュースアプリで日々のトレンドを追いかける習慣をつける。業界に関する時事問題が出題されることもあるので、自分が志望する業界の最新動向には常にアンテナを張っておく。
-


面接
-
自己PR・志望動機をしっかり言語化
-
面接官は限られた時間の中で「この学生を自社に迎えるべきか」を判断する。面接の冒頭から結論をわかりやすく伝えることで、アピールポイントを印象づける。
-
-
逆質問の用意
-
面接の終わりに「何か質問はありますか?」と聞かれるケースが多い。ここで真剣度や企業研究の度合いを測られるため、企業の事業内容や社風に関連する具体的な質問を準備しておく。
-
-
オンライン面接の注意点
-
カメラの位置や背景、通信環境は事前にチェック。画面越しでも表情や声のトーンが面接官に伝わりやすいよう、少しオーバーアクションを心がけると良い。
-
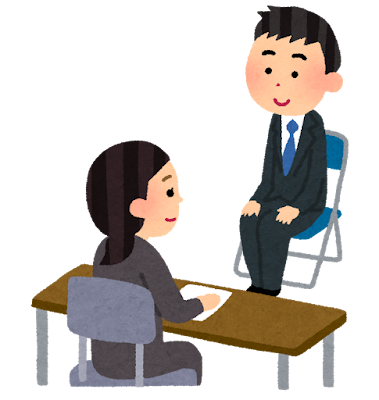

グループディスカッション(GD)
-
役割を考慮して参加する
-
「リーダー」「書記」「タイムキーパー」など、グループ内で役割分担することが多い。進んでやってみたい役割があれば、遠慮せずに引き受けることでアピールにつながる。
-
-
発言内容だけでなく、進行への貢献も評価される
-
自分の意見を押し通すだけでなく、他のメンバーの発言を引き出したり、まとめ役として議論を建設的に進める姿勢が重視される。
-

9. オンライン選考が増えるなかでの対策
コロナ禍を経て、企業の説明会や選考がオンライン化される流れが加速しました。地方在住の学生にとっては交通費や移動時間を節約できるメリットがある一方、コミュニケーション面で対面とは異なる難しさもあります。
1. オンライン説明会の活用
-
自宅や大学から参加できるため、複数の企業を効率的にまわることが可能。録画配信を行う企業もあるので、時間の調整がしやすい。ただし、積極的な質問がしにくい場合もあるため、チャット機能を活用したり、後日メールで問い合わせを行うなど工夫が必要。
2. オンライン面接のマナー
-
カメラのフレーム内に顔が中央に収まるようにし、背景はできるだけシンプルに。音声が途切れたり画面が固まったりする可能性があるので、事前に接続テストを行い、万が一に備えて連絡手段(電話番号など)を確認しておく。
3. オフラインの機会を大切に
-
オンラインが便利な反面、実際の職場や社員との対面交流から得られる情報は依然として貴重。可能であれば会社訪問やオフィス見学会など、直接足を運べる機会を作ると、志望動機もより具体的になる。

10. 27卒ならではの最新動向:コロナ禍後の就活と企業側の変化
コロナ禍は一旦落ち着きつつありますが、その後もビジネスのオンライン化や働き方の変化は加速しており、企業の採用活動にも以下のような影響を及ぼしています。
1. オンラインとオフラインのハイブリッド化
-
企業説明会やセミナーはオンラインが主流になりつつある一方で、最終面接や内定者懇親会などは対面で行う企業が増えてきています。特に最終面接は経営陣との直接対話を重視する傾向が強いようです。
2. DX(デジタルトランスフォーメーション)人材の需要増加
-
企業規模を問わず、デジタル技術を活用した業務プロセス改革が急務になっています。ITスキルやデータ分析力を持つ学生、またはその素養がある学生はさまざまな業種で注目されています。
3. 早期・通年採用の拡大
-
経団連の指針に縛られない企業が増えているため、大学3年生の夏から秋にかけて早期選考を行う企業はこれからも増えると予想されます。逆に本格選考解禁後の4~6月に参加するだけでは、出遅れる可能性もあるので注意が必要です。
11. OB・OG訪問・キャリアセンター活用のコツ
OB・OG訪問
-
目的の明確化
-
「社員の生の声を聞きたい」「業務内容や働き方の実態を知りたい」など、明確な目的を設定して臨むと、質問内容が具体的になる。
-
-
マナーを守る
-
連絡のやりとり、日程調整、訪問時の服装や態度など、社会人として最低限のマナーを心がける。訪問後はお礼のメールを送ることを忘れずに。
-
-
情報は複数の人から得る
-
1人のOB・OGの意見だけでは偏りがある可能性があるため、できれば複数の社員と話を聞き、総合的に判断すると良い。
-
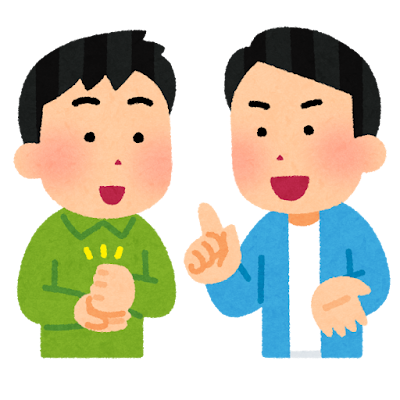

キャリアセンターの活用
-
模擬面接・履歴書添削
-
専門のキャリアアドバイザーがいる大学も多い。無料で利用できるケースが多いので、ESや面接での不安要素を相談してみよう。
-
-
求人情報の閲覧
-
大学独自の企業提携やOB・OGネットワークから得られる求人情報がある。大手の就活サイトにはない中小企業や地方企業の魅力的な求人が見つかることも。
-
-
就活イベントの情報収集
-
キャリアセンター主催の合同説明会やセミナーは、学内やオンラインで手軽に参加できるうえ、人数が比較的少ない場合もあるので企業と近い距離で話せるメリットがある。
-
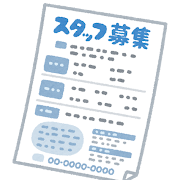
12. 内定獲得から入社までにやるべきこと
内定承諾前
-
複数内定を得た場合
-
自分がどんなキャリアを描きたいかを再確認し、企業の社風、業務内容、給与・待遇など総合的に判断する。可能であれば先輩社員に直接話を聞いてみるなど、最終的な決断に役立つ情報を集める。
-
-
返事を保留する場合
-
企業に対して誠実に連絡し、いつまでに回答できるかを明確に伝える。企業によっては保留期間を設けてくれる場合もあるが、あまりにも長引かせると印象が悪くなることもある。
-
内定承諾後
-
卒業論文や学業との両立
-
就活がひと段落すると、卒業までの学業に集中できるようになる。内定後も学校をおろそかにせず、きちんと卒業要件を満たすことが最優先。
-
-
内定者懇親会・研修への参加
-
企業によっては内定者同士の交流や職場理解を深めるイベントを用意している。積極的に参加して同期との繋がりを築くと、入社後の不安も軽減される。
-
-
必要書類や手続きの確認
-
健康診断、住民票、卒業証明書など、入社時に必要となる書類は企業から案内される。提出期限を守り、社会人としての第一歩をしっかり踏み出そう。
-
13. まとめ:自分らしい就活をスタートさせよう
就活のスケジュールは、年々早期化・多様化の傾向を強めています。27卒の皆さんは、大学3年生の夏~秋頃からインターンシップを積極的に利用し、本格的な就活開始(3年生の3月頃)に備えて自己分析や業界研究、エントリーシートの準備を進めることが望ましいでしょう。
しかし、「早く動かなければならない」という焦りから、自分の本当にやりたいことや将来のキャリアビジョンを見失ってしまうケースも少なくありません。就職活動はあくまで「自分の人生を考えるうえでの一つのプロセス」です。周囲のスピードや数値目標(何社エントリーする、何社受けるなど)にとらわれすぎず、自分自身が納得できる企業選びを心がけることが大切です。
企業側も、コロナ禍を経て採用活動の方法や求める人材像を柔軟に変え始めています。オンラインとオフラインを組み合わせた選考やインターンの実施、DXを推進できる人材の強化など、これまでとは違うアプローチをする企業も増えています。そんな変化の時期だからこそ、自分の強みを正確に把握し、それを具体的な行動やエピソードで示すことが内定獲得につながる鍵となります。
いずれにせよ、就活で最も大切なのは、自分を客観的に理解し、将来のビジョンに向かって主体的に動く姿勢です。選考がどのように進んでも、企業とのミスマッチを回避し、自分の価値観や目標に合った会社を選ぶことが、長期的なキャリア形成にとっては最善の道となるでしょう。情報戦になりがちな就活ですが、他人の意見に流されるのではなく、自分の軸をもって行動してみてください。
2027年卒業予定の皆さんには、まだ十分な準備期間があります。大学生活でしか得られない経験や学びを大切にしながら、就活準備も計画的に進めていってください。本コラムの内容が、その一助となれば幸いです。皆さんが自分らしいキャリアを実現できるよう、心から応援しています。